AOKIグループの祖業であり、「AOKI」と「ORIHICA」の2つのファッションブランドを展開する(株)AOKI。同社では、“ものづくりのAOKI・ORIHICA”として、とりわけ商品の品質にこだわってきました。そして、その品質の維持向上に重要な役割を担っている存在が、「繊維製品品質管理士(TES)」※です。
実はこのTES資格、合格率20%前後の狭き門で、かつ取得後も4年に1度の更新のために論文試験を受験する必要があります。そのなかでAOKI・ORIHICAは社員のTES取得を奨励し、現在商品部・品質管理部・ロジスティクス部79名のうち、約半数の40名が資格を保有。これは「百貨店・量販店・専門分野」の中で、競合他社や名だたる百貨店を抑えて1位の実績です(2024年1月22日現在)。
今回は、TESがAOKI・ORIHICAの商品・サービスの品質を実際にどのように支えているかを、同資格を保有する4人の社員に聞きました。
※繊維製品品質管理士(TES:Textiles Evaluation Specialist)は、繊維製品の品質管理に関する専門的な知識や技術を有する者を認定する資格。一般社団法人 日本衣料管理協会の実施するTES試験に合格すると取得できる。

PROFILE
株式会社AOKI
ロジスティクス部(物流) ゼネラルマネジャー加藤 光(かとう ひかる)
1991年度入社。AOKI・ORIHICAの店舗やECにおける物流のトータル管理を担当。

PROFILE
株式会社AOKI
ORIHICA商品部(レディース企画) リーダー兼田 佑美(かねだ ゆみ)
2009年度入社。ORIHICAでレディーススーツ、フォーマル、コートの企画(MD※1)を担当。

PROFILE
株式会社AOKI
品質管理部 チーフ岡田 知佳(おかだ ちか)
2014年度入社。AOKI・ORIHICAの商品クレーム対応や、品質管理教育を担当。

PROFILE
株式会社AOKI
ORIHICA商品部(メンズスーツ担当) チーフ海老澤 駿太(えびさわ しゅんた)
2019年度入社。ORIHICAでメンズスーツ、パーソナルオーダー、フォーマルの企画・在庫管理(MD・DB※2兼任)を担当。
- ※1 MD:マーチャンダイザー(商品の企画・開発や商品構成の決定、発注数量計画の立案などを専門とする職種)
- ※2 DB:ディストリビューター(商品の在庫を管理し、発注から商品売り切りまでの計画立案・管理などを専門とする職種)
難関資格合格に向けて、会社が受験をサポート
──TESは合格率が20%ほどの狭き門だそうですが、なぜでしょうか?
- 加藤:
- まず、科目が5つに分かれており、繊維の知識から商品不良時の対応まで幅広い知識が求められます。また3年以内に5科目すべてで合格しなくてはいけないことが理由として挙げられます。当社では、一発合格したのは資格保有者40人中、4~5人にとどまっています。実は、今日のメンバーの海老澤さんが、その一人です。
- 海老澤:
- 一発合格を目指して、フルスロットルで臨みました。
──受験に際して、どんなことが大変でしたか?
- 海老澤:
- なんといっても専門用語の多さに苦労しました。例えば生地の織り方や、素材の名称などですね。内容の理解よりまず先に、わからない用語の意味を、一つひとつテキストで確認する作業に専念する必要がありました。
- 岡田:
- 私も用語のなじみのなさ、そして科目数の多さに苦労しましたね。テキスト5冊分の情報を試験日までに全部読み切れるか不安だったので、毎日の仕事終わりや休日にカフェで学生みたいに勉強しました。
- 兼田:
- 私は日々の業務に追われて余裕がないなか、学習時間を捻出するのに苦労しました。そもそも社会人になって以降、試験勉強をすることがなかったので、あらためて学習を習慣化すること自体が大変でした。
- 加藤:
- 私が受験したのは20年以上も前で、今とは事情が違いました。今は過去問題集が3年分ありますが、当時はまだなかったため、対策が難しかったです。仕事と並行して勉強するのも今ほど当たり前ではなく、その点も大変でした。
──TES受験に際し、会社からはどのような後押しがありましたか?
- 岡田:
- もちろん上限や条件はありますが、受験費用や、4年に1度の更新費用は会社がサポートしてくれます。
- 加藤:
- それと品質管理部が主体となり、TES受験者のための勉強会も実施していますよね。
- 岡田:
- はい、毎週水曜の9時半~10時に、受験者が集まる学習会を開催していて、毎回10人くらいが集まります。そこでは、事前に出題範囲を伝えて小テストを実施したり、繊維関連の検査機関にいた方も運営側に加わって学習のポイントを伝えたりしています。同じ目標を持つ者同士が定期的に集まることで、学習を習慣化し、かつ知識を身につけやすくすることがねらいです。
- 兼田:
- 特に「クレーム事例」と「論文」について、解答のコツや対策を重点的に指南してもらい、とても助かりました。さらに、練習問題の添削とアドバイスもしてもらえます。
- 海老澤:
- やっぱり練習問題の答えだけを見ても、なぜそうなるのかわからないこともあるので、人に聞いて理解を深められる意義は大きいですよね。
- 岡田:
- 私は勉強会の運営を通して、自分自身の復習の機会にもなっています。
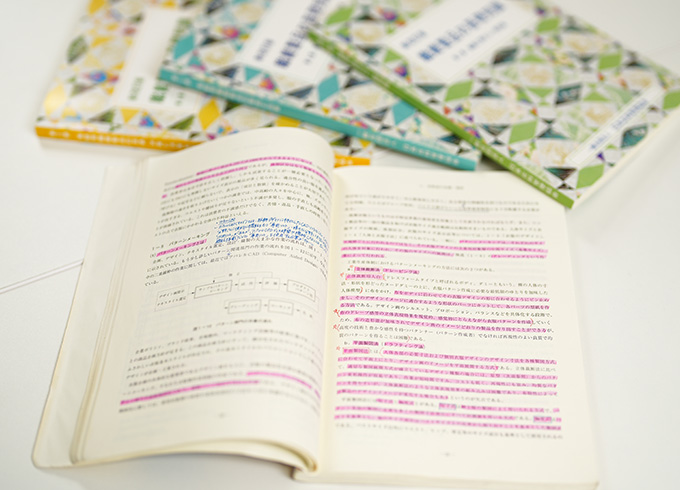
TESの知識が、商品の品質管理体制の“底上げ”につながっている
──TES資格は、ご自身の業務にどう活きていますか?
- 兼田:
店舗スタッフから相談があった際、商品の取り扱い方法や商品不良を起こさない対策について自信を持ってアドバイスできるようになりました。また、素材特性に合わせたものづくりや事前の対策ができるようになり、担当商品での不良品件数が減少したと感じています。
特に、レディースはメンズよりも素材のバリエーションが豊富で、扱いが難しいケースも多いです。だからこそ、素材を見た段階で起こり得る商品不良を予測し、事前にメーカー様に相談して改善をお願いし、未然に防ぐことが大切です。
──TESの知識が活かされるのは、具体的にどんな場面ですか?
- 兼田:
- 例えば、店舗に陳列する紺色のスーツが、少しムラ状に変色してしまったことがありました。生地は紫外線などによって色あせることがありますが、ムラ状に変色する例は見たことがありませんでした。そこで陳列場所の状況を調べたところ、道路の排気ガスが店舗に入り込んでいることが原因のようだったので、ただちに対策を講じました。原因によって変色の仕方もさまざまであると、まさにTESのテキストに書いてあった通りのことが実際に起きていたというわけです。
- 加藤:
私も商品部でメンズスーツのMDを担当していた時に、同じような経験があります。襟が赤く変色して返品された商品があったのですが、生産時の生地試験では、光に対する堅牢度※も汗に対する堅牢度も基準以上でした。ところが、光と汗をかけ合わせた耐性試験を行ったところ、非常に低いデータが出たんです。このように、商品不良の原因追及や新たな試験方法を検討する上で、TESの知識が活きています。
※堅牢度:生地の変色や色落ちのしにくさの程度を表すもの。
- 海老澤:
以前は、メーカー様から素材の説明を受ける際にすぐには理解できないことがありましたが、TESの勉強をしたことでその場で理解できるようになりました。やはり、素材が繊維から糸、生地になって製品になるという一連の流れを勉強したことが、とても役立っています。
それにより、その生地の特性や使用時のメリット・デメリットに対する理解も早くなったなと。おかげで以前は色・柄・質の実現可否について、その都度メーカー様に相談していたのが、TES取得後は、ある程度の実現性を想定したうえでメーカー様に相談するという、一歩、二歩踏み込んだアプローチができるようになりました。- 岡田:
- 私も商品部でレディースインナーのMDを担当していた時、TESを取得したことで商談時に出てくる生地名がわかるようになったり、お客様からの商品不良のお申し出に対してスムーズに対応できるようになったりと収穫は大きかったです。品質管理部に異動してからは、それがより身近になった形で、商品不良の原因追及にTESの知識を活かしています。
- 加藤:
物流管理の業務では、物流センターに納品される商品に品質不良があった場合、輸送前の工程を担う品質管理側と、輸送を担う物流側のどちらに問題があったのかがわかりません。したがって、それを究明したうえで、次回の商品発注に向けてフィードバックする必要があります。その一連の業務にも、TESの知識が役立っています。
AOKI・ORIHICAの最終目的は、品質的に間違いないものをお客様に届けることです。その実現には、各取引先様にも品質に対して同じ意識を持っていただくことが大切です。TESの知識は、そうした意識共有を図るきっかけとなり、TESがAOKI・ORIHICAの品質管理体制の“底上げ”につながっているともいえます。
- 海老澤:
- 品質に対する理解が深いTES取得者が多いことで、取引先様に「AOKI・ORIHICAの高い品質基準に応えられる素材を納品しよう」と意識していただけているとも思います。

初めての商品でも“絶対に商品不良を起こさない”が目標
──そうしたTESの知識を活かし、今後どのようなことを心がけて業務に臨んでいきたいですか?
- 兼田:
- 新しい商品をつくる時や新しい素材を使う時こそ、例えば事前に試験を行って品質管理部に相談したり、何か対策を講じたりと細かく段階を踏むようにしています。そうして「新しい商品でも絶対に商品不良を起こさない」ことを、今後も目標にして取り組んでいきたいです。
- 加藤:
- 「3H」と呼んでいる、「初めて」「変更」「久しぶり」の素材・生地・縫製工場等を選定した時は、特に慎重にやりましょうということですよね。それが社内の共通認識となっています。品質問題が発生した際、「商品の企画~生産~物流~店舗」どの段階で発生したのか、事象と改善策を明確にし、その情報を蓄積・社内共有することで、品質向上に取り組んでいきたいと思います。
- 海老澤:
- スーツはビジネスで使う実用品であり、お客様の日常に大きく関わるものです。だからこそ、企画段階から「着るたびに気持ちがプラスになる商品」を提供できるように、素材や品質を改善しながら商品企画に取り組んでいきたいです。
- 岡田:
- 私は、お客様からの要望を聞く“アンカー”的な部署にいます。したがってご要望をいち早く分析し、改善できるものは商品部にしっかり伝達することや、不良品があればすぐに店頭から引き上げることが重要になります。まさに商品不良時の事例別の対策は、TESでしっかりと学ぶことなので、その知識を活かしながら、今後もお客様の手元に届く商品の質を高めることに努めていきたいです。
- #ファッション
- #ものづくり



![あなたのために、働く服。高機能レディースウェア・ブランド『MeWORK』[後編]](/stories/project/img/mework-second-pageMain.jpg)
![あなたのために、働く服。高機能レディースウェア・ブランド『MeWORK』[前編]](/stories/project/img/mework-first-pageMain.jpg)

